人は思う、「自分は戦争に関わらない。」
だが、どちらにつくのか選択を強いるのが戦争だ—-
とこの映画は語っている。
ヒトは様々な判断、そして選択を強いられる。戦時下において、それは自分の命はもちろんのこと、家族や周囲、あるいは何の縁もゆかりもない人にまで影響を及ぼす。
その重圧は平時のそれとは比較にならないほど、重く、そして過酷であること。まして自身が女性であるならば、それは(おそらく、たぶん、きっと)男のものより強い。
横浜に出かけたついでに黄金町にある映画館ジャック&ベティで観た映画は、実在の女性 ソニア・ヴィーゲットをモデルとした「ソニア — ナチスの女スパイ」。

映画の公式サイトはこちら
1913年にノルウェーで生まれ、自国はもとよりスウェーデン、デンマーク、フィンランドで舞台女優として活躍。邦題タイトルにはナチスの女スパイあるとあるが、その前に41年にレジスタンスに参加し、その後スウェーデンのスパイとして活動を始めている。持前の美貌を武器にナチスの最高位となる国家弁務官テアボーフェンに接近、そこからもスパイを依頼(という形だが、父親を強制収容所に収監しているのだから脅迫の混じった強要)され、結果として2重スパイとなる。スパイ活動はヒトに知られず、その表面から実態をうかがい知ることはできない。このため、周囲からはナチスのシンパと思われることになった。映画では、男性がソニアのポスターに唾を吐くシーンや父親とのいさかいとして描かれている。このことは戦後にも尾を引いたのだろう1969年にスペインへ移住し、ここで1980年に亡くなった。死後25年が経過したのち、スウェーデン情報機関のアーカイブが公開され事実が明らかになったとのこと。
ナチスを描いた映画ということで、残虐なシーンもあるかと思っていたら、直接的なシーンはなく、会話や写真(ソニアが密かに撮影する)で示される程度。だが、ソニアがスパイ活動するにあたり、いつその正体がばれてしまうのか、あるいはマリアというドイツ側のスパイを見つけようとしたりで、ハラハラ、ドキドキさせられ、なかなかスリリングなのだ。
ソニアを演じた女優(イングリッド・ボルゾ・ベルダル)は、際立って美しいというよりも、知性を感じさせる大人の女性。謎の人物アンドル(ハンガリー大使館所属)との交流を描くシーンは美しい。戦争が終わったらニューヨークへ、それもBlue Noteへ行きたいと話すアンドルがソニアのためにジャズ・バー(?)でピアノを弾くのだが、そこで弾かれた曲は、当時の、つまり1942年ごろのジャズのイディオムからは進みすぎているのように思える。
この当時は、(いわゆる)スウィングの時代 — 大戦中に慰問楽団を率いてツアーを行い、44年にイギリスからフランスへ渡るのに搭乗した軍用機で消息不明となったグレン・ミラーを思い浮かべるとよい。 — であり、ビバップはアメリカで始まりかけたころ。「ジャズ」という言葉から思い浮かべるのは「モダン・ジャズ」のスタイルであり、それはビバップよりもっと後のスタイルになる。さらにアンドルのモダン・ジャズ風のプレイには、ゴスペル風の雰囲気すら混じり….
もしこの映画を観るならば、そのシーンがナチス占領下のノルウェーなのか、中立国スウェーデンなのかを想像しながら、がお勧め。そうでないとどんどん進行するストーリーを追い切れず、置いてきぼりにされてしまう。
サウンドトラックが聴けるサイトはこちら
この当時のスウェーデンの雰囲気は佐々木譲の小説「ストックホルムの密使」を読むとわかる。
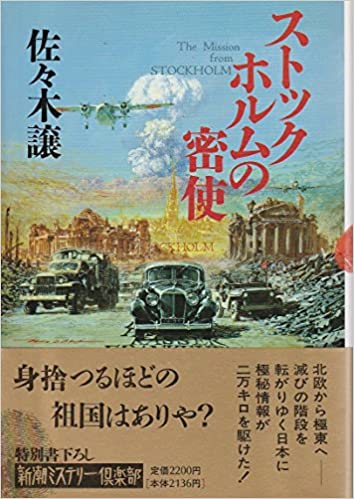
ナチス側はもちろんスウェーデン側のスパイの元締めもなかなかエグく、配下のスパイ達に非情な命令をし使いまわす。結局は男側の論理ということなのだろうと。そのボスの風貌は仕事でやり取りのあったスウェーデン人にそっくりだった。

